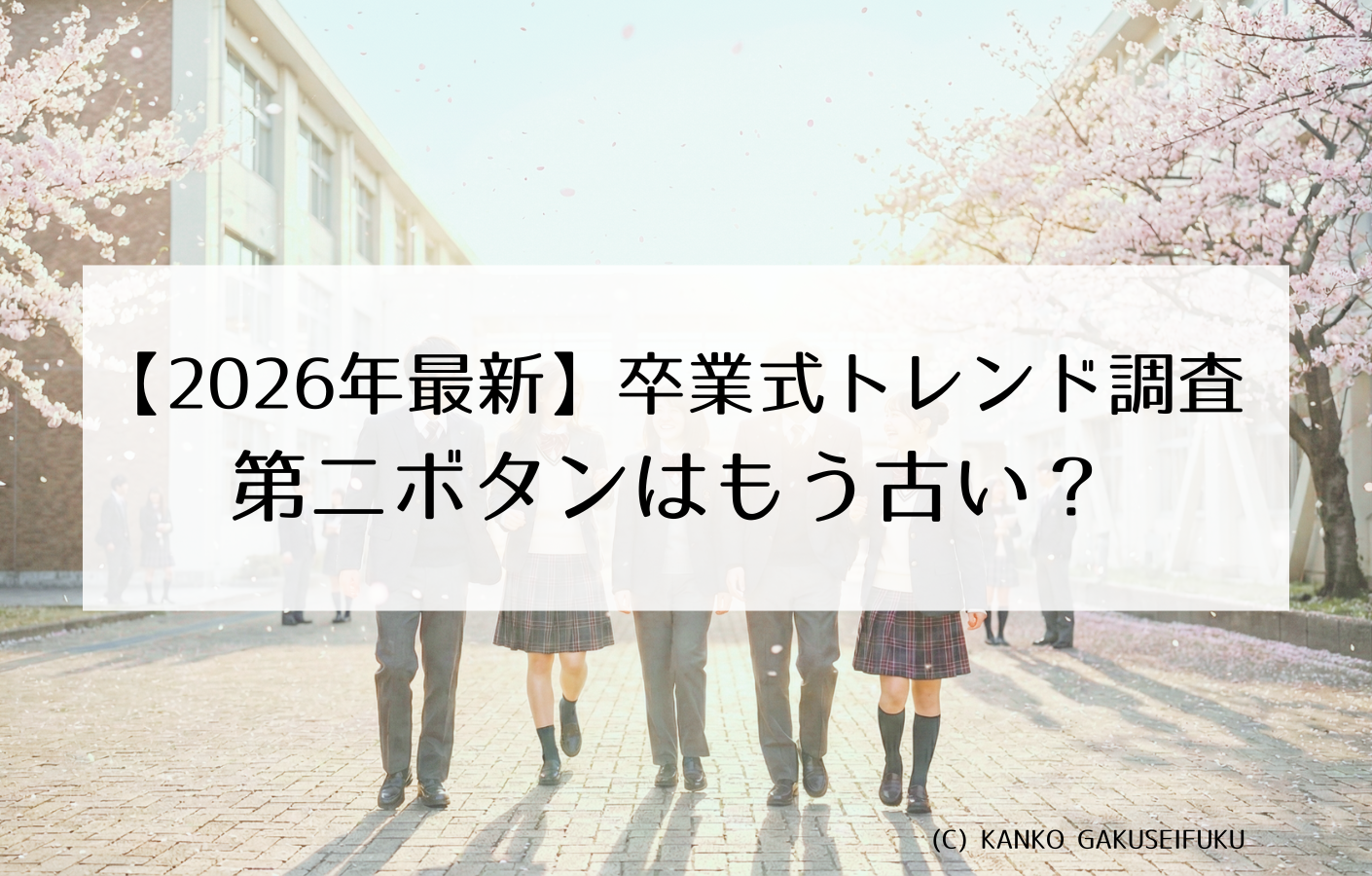2019.05.14 先生向けコラム 第3回 学力テストでは測れない“非認知能力”の必要性と大人にお願いしたいこと【生徒/後編】
岡山県倉敷市の学校法人ノートルダム清心学園 清心中学校・清心女子高等学校。社会が激変する中で、130年以上引き継がれている精神と新しいことに挑み続ける教員と生徒。一般社団法人 カンコー教育ソリューション研究協議会との産学連携キャリア教育プロジェクトを通じて、様々な立場からプロジェクトでの変化やこれからの学びについて語っていただきました。(全7回)

全33チームから企業が選定した受賞チーム「Spirits」の生徒へ、副賞でもある本記事インタビューを実施。後編では、これから必要な資質・能力として、幼児教育や子育て、ビジネスや人財育成などで注目が高まっている、学力では測れない“非認知能力”。今回は、生徒自身はどう考え、必要としているのか、そして大人がサポートできることについて伺いました。(写真右から大槻さん、片山さん、藤原さん、丸山さん)
“非認知能力”は学力に影響があるのか
―― みなさんがセルフアセスメント(自己評価)をした10項目は、いま注目されている、学力では測れない“非認知能力”といわれるものです。数値で測れない力全般なので、コミュニケーション能力やチームワーク、社会人基礎力もあてはまります。これからの時代に必要な能力として、働く人や先生、子どもを育てる保護者向けなど様々な本が書店でも並び、注目されています。アメリカのある研究では、非認知能力があるとないとでは、大学卒業後の年収に100万円もの差があったという事例もあるんですよ。
みなさん:え!そんなにも違うんですね!私もそうなりたい!

年収の話に大きく反応する生徒のみなさん
―― そんな力をみなさんは、自分で高まったと気づきました。話を聞いていかがですか?
丸山さん:たしかに、社会に出たときに必要になる力だと感じました。話し合いをするときに案を出したり、物事を別の角度から考えられるようになると思います。例えば、筆箱があったとしてマーケティングを体験するまでは「かわいい」と自分の感情しかでてこなかったのが「このぐらいの年代向けかな」「なんでこのデザインなんだろう」など考えられるようになりました。
―― 視野が広がりましたね。では、みなさんは“非認知能力”が高まることで、学力にも影響があると思いますか?
藤原さん:学力にも相互していいこと…。問題を解くときは、やり抜く力が必要になると思います。いろんな面から考えて、こっちで考えてだめだったら、こっちで。というのは数学や研究のときにも役に立つと思います。
片山さん:たしかに。自分を知ることができるのも、ひとつの影響になると思います。以前に研究発表用のスライド作りに家で取り組んでいたとき、家族から「あなた、そういうの好きだよね」と言われたんです。その言葉で「たしかに、つくったりデザインするの好きだな」と気づけた。自分の見方と他人の見方は違うので。それを他人がこういう集まりで「あなたのすごいところここだよ」と言ってくれるとそれを活かしてみよう、次はここをやってみようと、そのような影響があると思います。
藤原さん:そうだね、自分を知って、敵を知ることもできる。それは、テストの勉強にも絶対影響する。いやになるときがあるもんね。だけど、ビジョンがはっきりしてれば、いける。何があっても大丈夫そう。そこをちゃんと持つことは「テストでどのくらいの点数をとるぞ」とかにも応用できる。今回のプロジェクトも、コンセプトを軸にみんなで考えていけたから、創りあげることができた。その軸となる目標を定めることが、勉強でもみんなで何か取り組むときに必要なんだなということが勉強になりました。
聴きあう、受け入れ合う空間
― 生徒のみなさんはそのように感じたのですね。では、“非認知能力”を高めたり、自分が成長に気づくために大人にお願いしたいことはどんなことですか?
丸山さん:こういう機会をつくってほしいです。機会があるかぎり、積極的に参加していきたいです。
藤原さん:気づくために教えてほしい、言ってほしい。自分の向上した力を感じられるような課題をだすなど、変化を感じられる流れをつくってほしい。
片山さん:「何でもいいからやってみね(やってみたらを意味する岡山弁)」と言ってくれること。小さいころ、習い事をたくさんやっていた時期があり、そのときに習字をはじめたんです。それから10年間習字をして、最後は習字だけになりました。「とりあえず何でもいいからやってみね」と言ってくれた親に感謝しています。
藤原さん:そうだね、させてくれるって大事だね。
片山さん:あと、続けさせてくれることもありがたいです。習字を一度2か月くらいやめたとき、しばらくたったら「へたになってるかもしれんから、もう一回いってみたら?落ち着いてきたんだし」と言ってくれ「あ、じゃあいくわ」とまたはじめて、その一言で、今も続けられています。
藤原さん:たしかにいやになる時期は絶対あるもんね。そこでそんな言葉を言ってもらえると続けられる。
片山さん:楽しくなるまで、サポートしてくれたっていうのもあります
―― 「待つ」とか、ね(いち、子をもつ親としてかみしめながら)。
みなさん:たしかに! 笑
待つ側・待ってほしい側の両者に強く共感するみなさん
藤原さん:そうですね。何も言わずに待ってくれることが一番、ありがたい。
―― ついつい、言いたくなるんですよね。
藤原さん:わかります、いわれたら「ムッ」てなるけど、わかる。
―― さっきの丸山さんの話にもつながりますね。機会をつくる、続けたくなるように待って、また機会を促すようにつつくというか。
片山さん:そうですね、あと褒めるというのも効果的です。嬉しいし、やる気が出ます。
藤原さん:うん、褒められて嬉しくない人はいないもんね。
―― ありがとうございました。プロジェクトのふりかえりから、子育てやチームで仕事をする一個人としてもみなさんの言葉や姿勢に大変勉強になりました。ひとまず今夜、子どもに対して「待つ、ほめる」を実践してみたいと思います。みなさんへのメッセージはありません。それぞれ自分なりの次の目標がみつかっていますからね。それに向かってみなさん、そのままでいい。素晴らしいです。お互いにがんばっていきましょう。ありがとうございました。
いかがでしたか? 関連記事では、様々な立場から教育やこれからについてお話いただきましたので、ぜひご覧ください。
本プロジェクトに関するお問い合わせは、上記お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
関連記事
(撮影 / 桑原 愛那、取材・ライティング / 北浦 菜緒)
探究学習のテーマはどう設定する?興味が湧く面白いテーマ例をご紹介
2023.06.28 先生向けコラム 探究学習の授業計画を立てるにあたって、テーマの設定に悩んでいる先生もいらっしゃると思います。この記事では、探究学習の課題点やテーマ設定のポイントについて解説しています。具体的なテーマ例も挙げていますので、ぜひ授業づくりにお役立てください。
学校広報とは?生徒に選ばれる学校になるために
2023.03.15 先生向けコラム 学校広報は以前より、生徒募集などさまざまな役割があります。 一方、少子化の加速やインターネット・SNSの普及に伴い、学校広報に求められる手法や視点が変化しているのも事実です。今回は、学校広報の「情報発信」についてご紹介します。
-
部活動地域移行とは。部活動改革のカギを握る“地域移行”の先行事例をご紹介
2023.02.23 先生向けコラム 長年にわたる学校教育の中で、部活動は重要な位置を占めてきました。また部活動は生徒の体力向上や人間関係の構築にも、大きく貢献してきました。ところが現在、社会の変化に合わせる形で、部活動の在り方が変わりつつあります。その流れに沿ってスポーツ庁や文化庁、文部科学省が中心になり、「部活動改革」の推進が始まり、今後さらに取り組みが進むことが予測されます。 具体的には、部活動の地域移行や、教員の働き方改革が行われることになりますが、こうした取り組みが教育現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。部活動改革の概要のほか、先行的に部活動の地域移行に取り組んでいる地域部活動推進事業モデル校の事例も含めてご紹介します。 -
学校でできるSDGsの取り組みをご紹介。中学生・高校生でもできる取り組み事例
2023.02.16 先生向けコラム 近年、持続可能な社会の担い手となる子どもたちの学ぶ力を育むため、様々な学校がSDGsを教育に取り入れています。 しかし、SDGsの取り組みで学校でできることは何なのか。学校教育にどのように取り入れたら良いのか悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。今回は学校で実際に行われている取り組み事例を8つご紹介します。 -
探究学習とは?基本から学校事例までご紹介。 どのようなテーマで行っているのか?
2023.02.01 先生向けコラム 高等学校の新学習指導要領の移行期間が終了し、2022年度から年次進行での実施となりました。多くの学校では既に「総合的な学習の時間」から「総合的な探究の時間」(以下:探究学習)として実施していることと思います。 ここで、改めて探究学習とは何かを解説し、学校での取り組み 事例を紹介いたします。