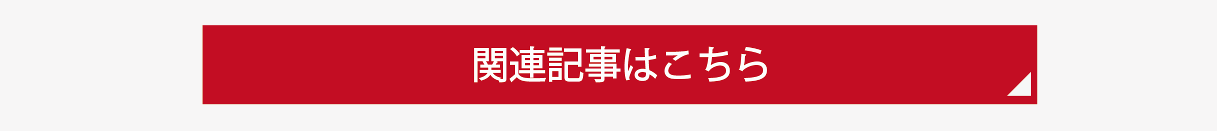2016.09.30 先生向けコラム 夢を視覚化することで不登校の子どもたちをもう一度学校へ
心の問題を抱える子どもたちの表現手段として「書き記す」意義について心理カウンセラー つだ つよし、さんに話をうかがいました。
ドリマ手帳を活用した心理カウンセリング
 最近の子どもたちは、不登校や無気力に限らず、言葉数がとても少ない印象を受けます。自分の気持ちや意見を表現できず会話に行き詰まる。悩みをギリギリまで心の内に抱え込むケースもみられます。
最近の子どもたちは、不登校や無気力に限らず、言葉数がとても少ない印象を受けます。自分の気持ちや意見を表現できず会話に行き詰まる。悩みをギリギリまで心の内に抱え込むケースもみられます。
しかし、そんな子どもたちも、文章にすると自分の思いや主張を表現できるんですね。当塾では、手帳や交換日記といったツールをカウンセリングの中に取り入れ、子どもたちが自分の将来や生き方について考えイメージできるよう、そしてそこに向かって足を踏み出せるよう、支援を行っています。
当塾が採用しているドリマプランナー手帳は、子ども自身が自分の考えや成長を「視覚化」できるのが特長。一週間の行動目標を立てて、自分ができたこと、できなかったことをチェックしたり、思いを振り返ったりすることで先の見通しが想像でき、自信へとつながっていきます。
不登校の問題を抱える子どもに対しては、起きてしまった過去よりも、これからどうすべきかを考えさせることがポイント。例えば、なぜいじめられたのか?と考えるのではなく、これからの人生をどう生きていくのかという視点に立つことが大切です。
学校に行ってもいいし、行かなくてもいい、というスタンスではなく、私自身は、子ども自らが「学校に復帰することは将来の自分にとって必要」と気づくことが肝要ではないかと思います。実際、学校を卒業したら誰も助けてはくれません。本人が自分でなんとかしなければいけないのが現実です。将来の道筋となる選択肢を与え、自分で自分の人生の可能性を広げていく、そのための支援をモットーに子どもたちに寄り添っています。
こころ応援塾
不登校になった児童生徒の早期学校復帰を目的として2015年につだ氏が設立。大分県奨励事業の指定を受け、心のケアに加え家庭学習支援を実施。初年度は受講生12名が全員学校復帰・進学を達成した。「無気力」で目的を持たない児童生徒へも支援を広げている。
プロフィール
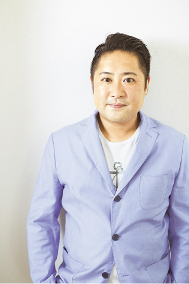 心理カウンセラー つだ つよし、さん
心理カウンセラー つだ つよし、さん
大分県の高校を卒業後、吉本興業福岡事務所に所属。その後、大分に戻りタレントや構成作家として地元メディアに関わる。子どもたちの夢を応援する番組「ダッシュくん」がきっかけで心理カウンセラーの資格を取得。不登校の子どもたちへの支援活動を行うとともに、全国の教育現場で子育て・教育をテーマとした講演活動も行っている。
探究学習のテーマはどう設定する?興味が湧く面白いテーマ例をご紹介
2023.06.28 先生向けコラム 探究学習の授業計画を立てるにあたって、テーマの設定に悩んでいる先生もいらっしゃると思います。この記事では、探究学習の課題点やテーマ設定のポイントについて解説しています。具体的なテーマ例も挙げていますので、ぜひ授業づくりにお役立てください。
学校広報とは?生徒に選ばれる学校になるために
2023.03.15 先生向けコラム 学校広報は以前より、生徒募集などさまざまな役割があります。 一方、少子化の加速やインターネット・SNSの普及に伴い、学校広報に求められる手法や視点が変化しているのも事実です。今回は、学校広報の「情報発信」についてご紹介します。
-
部活動地域移行とは。部活動改革のカギを握る“地域移行”の先行事例をご紹介
2023.02.23 先生向けコラム 長年にわたる学校教育の中で、部活動は重要な位置を占めてきました。また部活動は生徒の体力向上や人間関係の構築にも、大きく貢献してきました。ところが現在、社会の変化に合わせる形で、部活動の在り方が変わりつつあります。その流れに沿ってスポーツ庁や文化庁、文部科学省が中心になり、「部活動改革」の推進が始まり、今後さらに取り組みが進むことが予測されます。 具体的には、部活動の地域移行や、教員の働き方改革が行われることになりますが、こうした取り組みが教育現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。部活動改革の概要のほか、先行的に部活動の地域移行に取り組んでいる地域部活動推進事業モデル校の事例も含めてご紹介します。 -
学校でできるSDGsの取り組みをご紹介。中学生・高校生でもできる取り組み事例
2023.02.16 先生向けコラム 近年、持続可能な社会の担い手となる子どもたちの学ぶ力を育むため、様々な学校がSDGsを教育に取り入れています。 しかし、SDGsの取り組みで学校でできることは何なのか。学校教育にどのように取り入れたら良いのか悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。今回は学校で実際に行われている取り組み事例を8つご紹介します。 -
家庭科の授業に活用できるSDGsを取り入れた授業例
2023.02.01 先生向けコラム 2022年度から高校の教材などに大きく取り上げられるSDGs。家庭科の先生方もどのようにSDGsを家庭科の授業に取り入れていくか検討していらっしゃるのではないでしょうか?この記事では家庭科授業を実践されている先生にインタビューを行い、なぜ家庭科の授業でSDGsを取り入れたのか、どのようにSDGsを授業に落とし込んでいったのかを中心に紹介していきます。