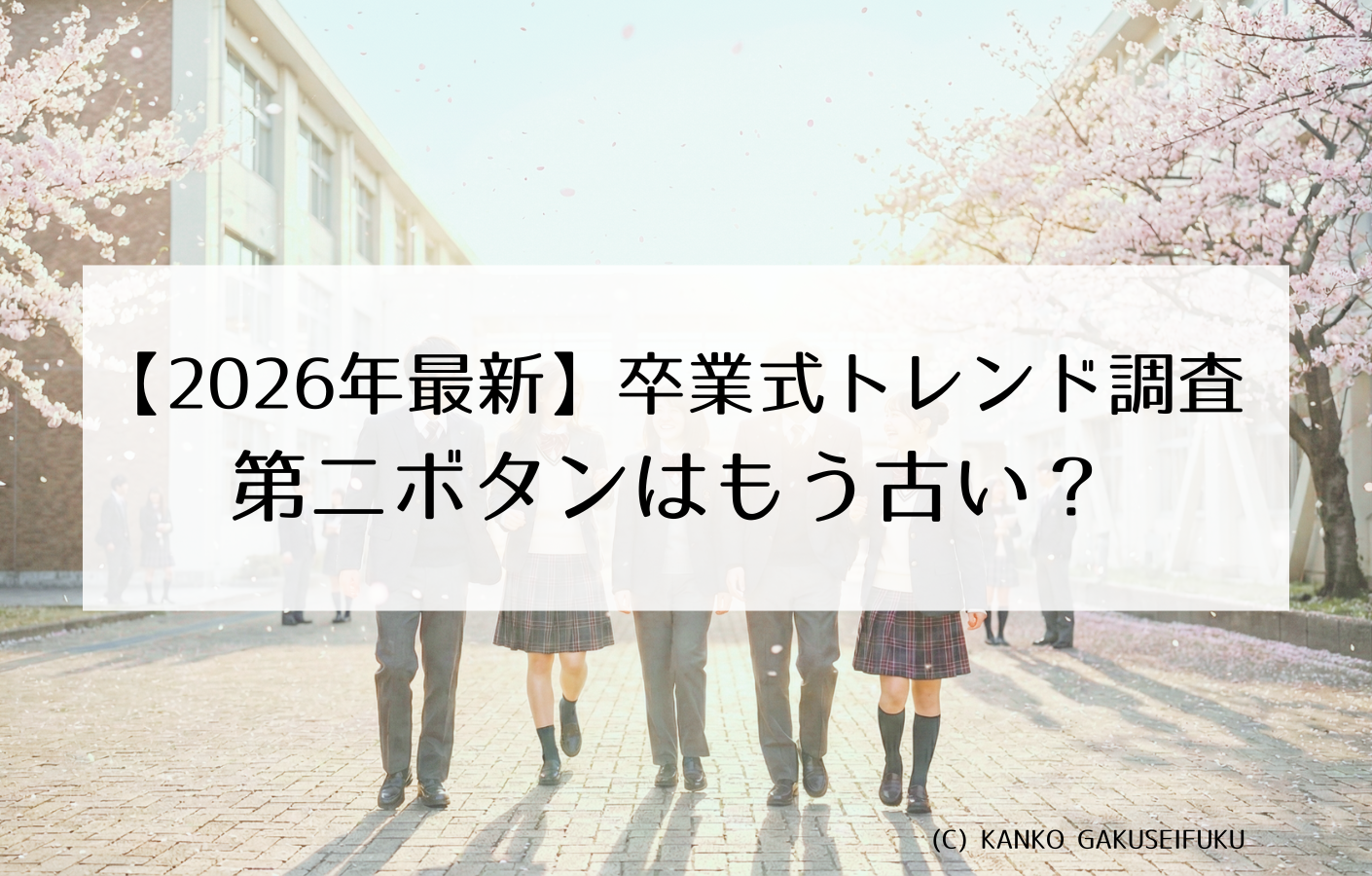2015.05.20 先生向けコラム 目標を共有し「チーム力」を育む (公益財団法人 日本中学校体育連盟会長 松岡 敬明 氏)

まつおか・たかあき
全日本中学校長会 会長
(公財)日本中学校体育連盟 会長
昭和30年3月東京都生まれ。明治学院大学文学部英文学科卒業後、東京都公立中学校教諭、東京都教育庁人事部指導主事、東京都教育庁指導部指導主事、渋谷区教育委員会指導主事、杉並区教育委員会指導室長、東京都教職員研修センター教育開発課長などを歴任。現在、東京都武蔵野市立第一中学校校長
異年齢の集団による心の発達
文部科学省の指針として、現在の部活動は学校教育活動の一つとして明確に位置づけられており、学校生活の中で授業と同じように大きな役割を担っています。特に中学生にとっての体育系部活動は、体力の基礎を養うという意味でも重要な活動といえますね。
私は、校長として新入生一人ひとりと個人面談を行うのですが、「中学生になって、小学校時代に想像していたことと一番違うと感じることはなに?」と聞くと、「部活の先生や先輩が親切に教えてくれる」と答える生徒が意外に多いことに驚きます。さらに「3年後はどんな自分でありたいですか?」と聞くと、部活をしている生徒からは「下級生から信頼され尊敬される存在でありたい」という答えが返ってきます。
部活を通して異年齢と交わり、先輩に対して同級生の友だちとは違う一種の「憧れ」を抱く。直近の目標となる人生モデルをそこに見出すのではないかと思います。
教員の仕事は「人を育てる」こと
体育系部活動に関していえば、競技には必ずルールがあり、ルールを守らなければ試合に勝つことはできません。これは、社会規範や秩序を学ぶことにもつながります。また、スポーツは、頭で理解して分かる授業とは違い、身体を動かしてコツをつかみ、感覚や技術を身につけていくわけですから体験的要素が非常に大きい。同時に、日常の練習や競技を通して、苦しさや悔しさ、そして喜びや感動など、メンタル面での経験も養われます。
さらに部活動を通して育まれるものとして「チーム力」が挙げられます。チームは単なるグループとは違って、メンバー全員が同じ目的意識を共有します。能力も性格も個々に違う生徒が、目標に向かって心を一つにして練習に励む。たとえ主力で活躍できなくても、チームの一員として自分にできる役割を見出しながら努力する。そこに、利己心を抑制し、他者を生かす思いやり精神も生まれるのではないのでしょうか。先輩との上下関係や礼節、仲間との協調は、いうまでもなく社会性を磨く基礎になります。まさに部活動は、生きるために必要なさまざまなスキルを身につけることができる貴重な教育の場だと実感しています。
指導する教職員へは、子どもたちへの接し方として、「結果」に対する評価だけではなく「プロセス」に対する評価も大事にしてほしいと思います。中学生は心身ともに発達途上の年齢です。「ここはできた」「ここはがんばれた」と、現時点での努力を認めながら、心と身体の成長を見守ってほしいですね。
探究学習のテーマはどう設定する?興味が湧く面白いテーマ例をご紹介
2023.06.28 先生向けコラム 探究学習の授業計画を立てるにあたって、テーマの設定に悩んでいる先生もいらっしゃると思います。この記事では、探究学習の課題点やテーマ設定のポイントについて解説しています。具体的なテーマ例も挙げていますので、ぜひ授業づくりにお役立てください。
学校広報とは?生徒に選ばれる学校になるために
2023.03.15 先生向けコラム 学校広報は以前より、生徒募集などさまざまな役割があります。 一方、少子化の加速やインターネット・SNSの普及に伴い、学校広報に求められる手法や視点が変化しているのも事実です。今回は、学校広報の「情報発信」についてご紹介します。
-
部活動地域移行とは。部活動改革のカギを握る“地域移行”の先行事例をご紹介
2023.02.23 先生向けコラム 長年にわたる学校教育の中で、部活動は重要な位置を占めてきました。また部活動は生徒の体力向上や人間関係の構築にも、大きく貢献してきました。ところが現在、社会の変化に合わせる形で、部活動の在り方が変わりつつあります。その流れに沿ってスポーツ庁や文化庁、文部科学省が中心になり、「部活動改革」の推進が始まり、今後さらに取り組みが進むことが予測されます。 具体的には、部活動の地域移行や、教員の働き方改革が行われることになりますが、こうした取り組みが教育現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。部活動改革の概要のほか、先行的に部活動の地域移行に取り組んでいる地域部活動推進事業モデル校の事例も含めてご紹介します。 -
学校でできるSDGsの取り組みをご紹介。中学生・高校生でもできる取り組み事例
2023.02.16 先生向けコラム 近年、持続可能な社会の担い手となる子どもたちの学ぶ力を育むため、様々な学校がSDGsを教育に取り入れています。 しかし、SDGsの取り組みで学校でできることは何なのか。学校教育にどのように取り入れたら良いのか悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。今回は学校で実際に行われている取り組み事例を8つご紹介します。 -
家庭科の授業に活用できるSDGsを取り入れた授業例
2023.02.01 先生向けコラム 2022年度から高校の教材などに大きく取り上げられるSDGs。家庭科の先生方もどのようにSDGsを家庭科の授業に取り入れていくか検討していらっしゃるのではないでしょうか?この記事では家庭科授業を実践されている先生にインタビューを行い、なぜ家庭科の授業でSDGsを取り入れたのか、どのようにSDGsを授業に落とし込んでいったのかを中心に紹介していきます。