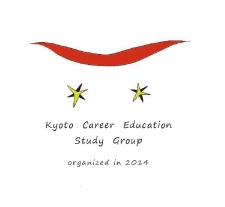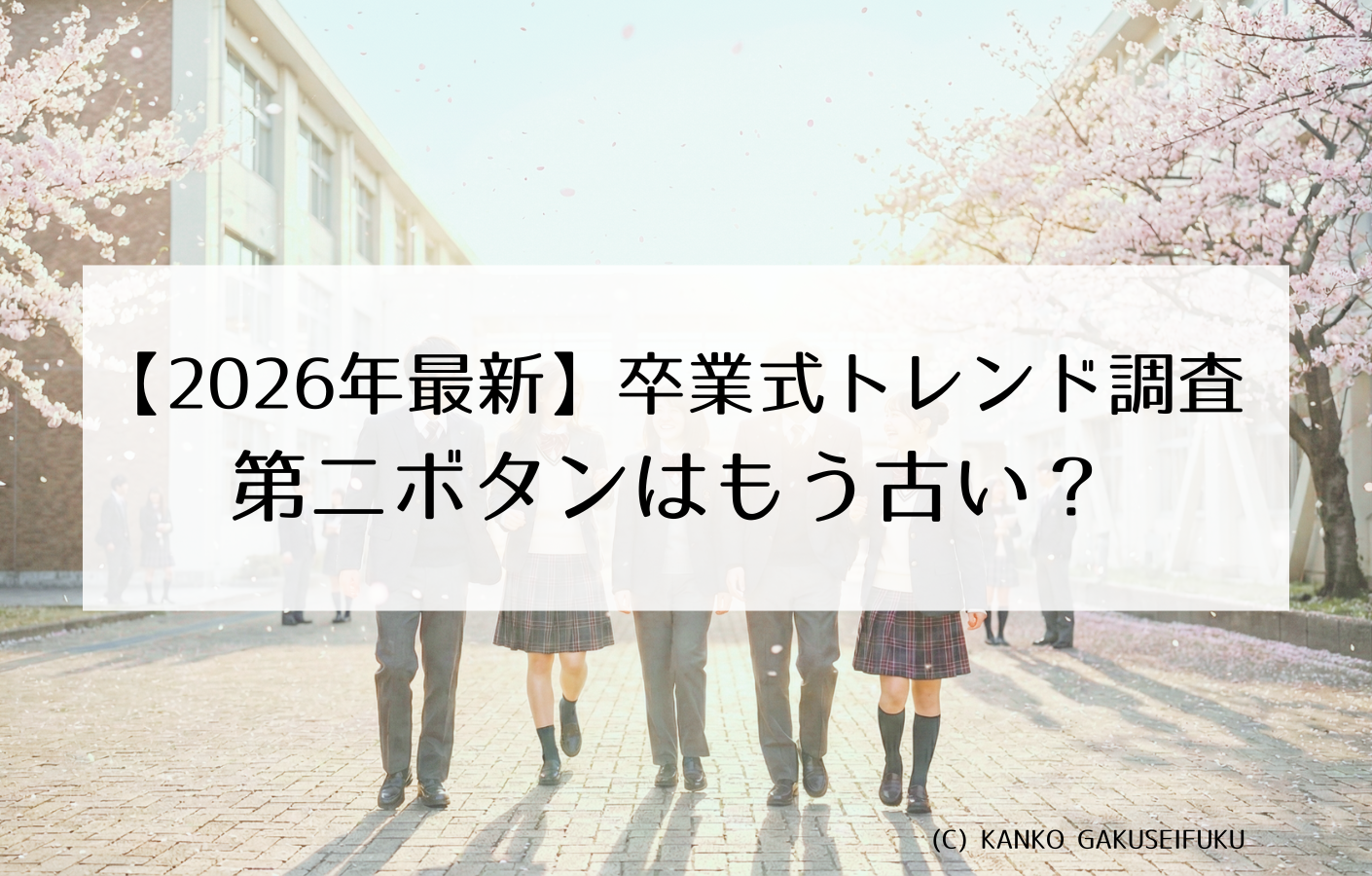2017.04.17 先生向けコラム 先生たちでつくる私設研究会「京都キャリア教育研究会」
「京都キャリア教育研究会」は京都府宇治市の先生たちが中心となって発足した私設研究会。会長の菊井雅志先生をはじめ、若い教員を中心に、大学から小学校まで約15校40人が参加。先生たちが抱える「多忙」や「不安」などさまざまな課題と向き合い、先生自らアクテイブ・ラーニングを実践しています。
草の根活動で現場から情報発信
京都キャリア教育研究会 会長
菊井 雅志先生
私も以前は「キャリア教育=職場体験」という誤った認識でしたが、2013年に教育研修センター主催で行われたキャリア教育指導者養成研修を受講した際、「子どもの将来を思い描いて、その目標に向かいどのように導くのか」というキャリア教育の根本を知り、感銘を受けました。当時、学年主任として進路指導に携わっていた私は、子どもたちには自分の意志で進路を決める自信を持ってほしいと考えていました。自分が目指しているものはキャリア教育ではないか、それが研究会を立ち上げたきっかけです。
研究会の主義は「草の根活動」。トップダウンでなく現場に原動力があるので、参加している先生たちのモチベーションは高く、現場からキャリア教育を発信すんだと意気込んでいます。小中高の先生だけでなく、大学の教員、将来教師を目指す教職大学院の学生も参加。時には教育界で有名な方を講師に招くなど、先生たちが刺激を与える場としても活用しています。
部会運営は部会長に任せており、テーマは先生たちの興味のあるものや、それぞれが教育現場で感じる「不安」など。不安や悩みは誰でも抱えているものなので、それをみんなで目を向けて考え共有することは、解決のヒントを導き出すことにつながります。また悩んでいた先生自身も救われると思っています。
特に若い先生は、何か分からないまま目の前の仕事に追われ、頑張っているのに充実感が少なく、不安もたくさん抱えています。そういう状況では、子どもの将来を思い描くことは難しいでしょう。学校内でのヨコのつながりを強めていくことはもちろん、校種を超えて子どもたちの成長を見守るタテのつながりも大切だと考えています。
キャリア教育は外部連携が大切だと思われがちですが、学校内で子どもをどのように育てたいかという意識が核としてあることが最も重要。先生たち自身も「子どもをどのように導いて行きたいか」という目標があれば、それに向かって指導ができ、目標に近づいていくことで、充実感を得られると思います。私たちはそういった意識を各学校の中で醸成していきたいと思っています。
今はまだ「京都」の中での見方で研究をしていますが、この活動が他の都道府県にまで広がって、地域をまたいだ交流ができることが私の理想です。今後も研究会がいろんなことを発信することで、先生たちが自由な発想ができるようになってほしいですね。
研究会を通じ、やりがいを実感
京都キャリア教育研究会
組織・多忙部会 部会長
吉岡 稜太先生
現在、「組織・多忙部会」の部会長を務めています。研究会に入ったのは菊井先生に憧れてです(笑)。実は菊井先生は私が中学生の時の担任の先生でした。部会長として、いざ多忙について考えてみてもなかなかテーマが定まらず、菊井先生に相談したところ「自分らしく楽しく働ければ、多忙でも“多忙”と感じなくなるのでは」とアドバイスをいただき、「多忙感」をテーマに研究を始めました。
私は小学校教諭なので、専門外の教科も教えなければいけません。苦手意識を持つ教科があればなかなか授業の見通しも立てにくく、それが負担となって多忙感にもつながっていると思います。そこで自分の専門である保健体育で、水泳の系統表を作成することに。中学校に進学するまでにできるようになってほしい目標を明記することで、体育が苦手な先生でも指導の見通しが立てられるように配慮しています。系統表を作ることで、自分がどのようなことを考えて、教えようとしているのか、他の先生方にも共有してもらいたいという思いもありました。
今後、体育だけでなく、国語や算数といった教科でも系統表を作成し、多くの先生が見通しを立てながら子どもたちを指導できるようにしていきたいと思っています。
私自身この系統表を作っているときは、子どもたちが上達していく姿を思い描け、楽しく充実感でいっぱいでした。また自分自身、指導をする上で整理ができ、多忙の中でも余裕を持って働けるようになり、意欲にもつながっています。
やりがいを持てれば、忙しくても目標に向かっている充実感を得られる、部会活動を通じて、学んだことが実際の現場でも活かせるように取り入れていきたいです。私自身多忙でスケジュールをまだうまく管理できていませんが、研究会活動もしっかり続け、仕事との両立を図っていけるよう努めていきたいです。
活動紹介
同研究会には「組織・多忙部会」「意欲向上部会」「コミュニケーション部会」「積極性向上部会」の4つの部会があり、仕事の合間をぬって会合を実施しています。また夏と冬の年2回、研究大会を開催し研究成果を発表。今後はこれまでの総括や見直しを行い、次期の取り組みを再検討します。
研究会での検討事項を学校に導入する際は、管理職の承認を得て行い、年に1回活動紀要を作成し、報告も行っています。
活動事例
・職員室内の人間関係・チームワークについて考える研究では、参加者が所属する学校で検討事項を導入。先生間のコミュニケーションが図られたことで、生徒指導や教育相談などの担当教員の連携が強化され、生徒指導数が大幅に減少した。
・京都エリアに昔から推奨されている泳法「ドル平」(平泳ぎとドルフィンキックを合わせた泳法)の研修会を実施。「ドル平」の指導に不安を感じていた先生もいたが、指導方法やその有用性を学校内で共有でき、不安が解消できた。
ロゴマーク
「キャリア」の由来である「荷台」をモチーフにしたロゴマークには、子どもたちが自分の人格や選び抜いたものを載せ、自ら運んでほしいという期待が込められています。また星をかたどった車輪は教員を表し、子どもたちを支えながら、彼らの「星」でありたいという思いを込めています。
探究学習のテーマはどう設定する?興味が湧く面白いテーマ例をご紹介
2023.06.28 先生向けコラム 探究学習の授業計画を立てるにあたって、テーマの設定に悩んでいる先生もいらっしゃると思います。この記事では、探究学習の課題点やテーマ設定のポイントについて解説しています。具体的なテーマ例も挙げていますので、ぜひ授業づくりにお役立てください。
学校広報とは?生徒に選ばれる学校になるために
2023.03.15 先生向けコラム 学校広報は以前より、生徒募集などさまざまな役割があります。 一方、少子化の加速やインターネット・SNSの普及に伴い、学校広報に求められる手法や視点が変化しているのも事実です。今回は、学校広報の「情報発信」についてご紹介します。
-
部活動地域移行とは。部活動改革のカギを握る“地域移行”の先行事例をご紹介
2023.02.23 先生向けコラム 長年にわたる学校教育の中で、部活動は重要な位置を占めてきました。また部活動は生徒の体力向上や人間関係の構築にも、大きく貢献してきました。ところが現在、社会の変化に合わせる形で、部活動の在り方が変わりつつあります。その流れに沿ってスポーツ庁や文化庁、文部科学省が中心になり、「部活動改革」の推進が始まり、今後さらに取り組みが進むことが予測されます。 具体的には、部活動の地域移行や、教員の働き方改革が行われることになりますが、こうした取り組みが教育現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。部活動改革の概要のほか、先行的に部活動の地域移行に取り組んでいる地域部活動推進事業モデル校の事例も含めてご紹介します。 -
学校でできるSDGsの取り組みをご紹介。中学生・高校生でもできる取り組み事例
2023.02.16 先生向けコラム 近年、持続可能な社会の担い手となる子どもたちの学ぶ力を育むため、様々な学校がSDGsを教育に取り入れています。 しかし、SDGsの取り組みで学校でできることは何なのか。学校教育にどのように取り入れたら良いのか悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。今回は学校で実際に行われている取り組み事例を8つご紹介します。 -
探究学習とは?基本から学校事例までご紹介。 どのようなテーマで行っているのか?
2023.02.01 先生向けコラム 高等学校の新学習指導要領の移行期間が終了し、2022年度から年次進行での実施となりました。多くの学校では既に「総合的な学習の時間」から「総合的な探究の時間」(以下:探究学習)として実施していることと思います。 ここで、改めて探究学習とは何かを解説し、学校での取り組み 事例を紹介いたします。